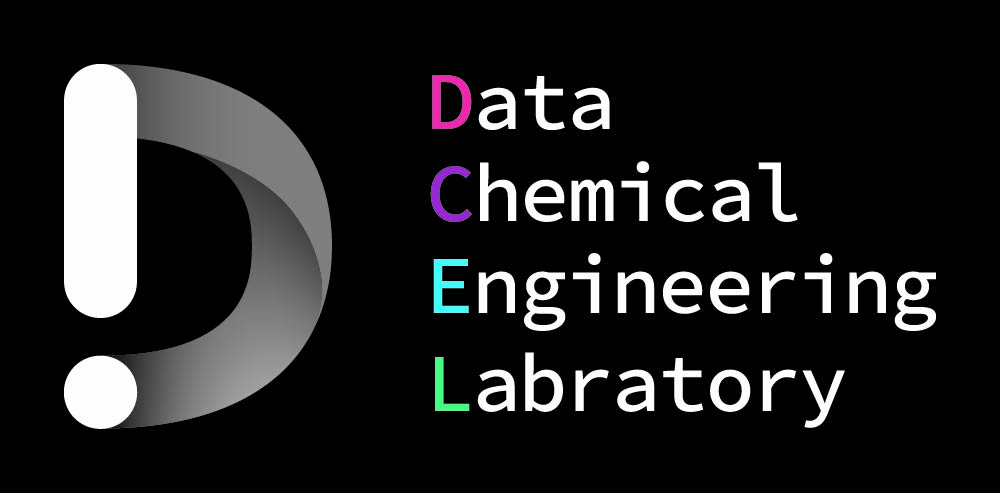分子設計・材料設計・プロセス設計・プロセス管理において、分子記述子・実験条件・合成条件・製造条件・評価条件・プロセス条件・プロセス変数などの特徴量 x と分子・材料の物性・活性・特性や製品の品質などの目的変数 y との間で数理モデル y = f(x) を構築し、構築したモデルに x の値を入力して y の値を予測したり、y が目標値となる x の値を設計したりします。
「外挿」を予測することがモデルに求められており、「外挿」の解釈についてはこちらに書いた通りです。

どの「外挿」も合わせて、「外挿を予測できる」という主張には注意が必要です。ひとえに「外挿を予測できる」と言っても、モデルの仕組み的に新しい種類の化合物、例えばトレーニングデータに含まれない元素を含む化合物の x を入力して単に y を「予測できる」だけなのか、あるいは外挿の化合物を内挿と同様の予測精度で「予測できる」のか、確認する必要があります。
単に外挿に相当するサンプルの x をモデルに入力できるだけであれば、現在は色々な仕組み・モデルが開発されているため、難しいことではありません。重要なことは、予測した y の結果が実際の y と合致するかどうか検証されていること、そして難しいこと・挑戦的なことは、外挿領域で良好に合致していることです。手法として「外挿を予測する仕組み」を提案・開発しているにもかかわらず、検証は外挿で行っていない、すなわち内挿の検証しか行っていない例も見受けられます。
繰り返しになりますが、モデルに求められている「外挿を予測できる」ということは、外挿を内挿と同程度の精度で予測できるということです。色々な論文を読む際や学会発表を聴く際、そして手法を検証・開発する際には、外挿をどの程度の精度で予測できるのかまで考えて検討するようにしましょう。
以上です。
質問やコメントなどありましたら、X, facebook, メールなどでご連絡いただけるとうれしいです。