学会発表、特に口頭発表のお話です。発表の流れや注意することについてはこちらに書いた通りです。
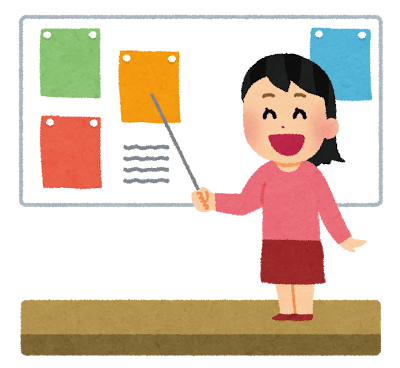
学会での研究発表 (口頭) の一般的な流れ
学生のころから学会において研究発表をする人もいらっしゃると思います。今回は、学会発表での話の流れについてまとめました。人や場面によって多少変わることもありますが、一般的な流れはこちらです。 自己紹介 発表の概要 背景 問題点 目的 方針 手...
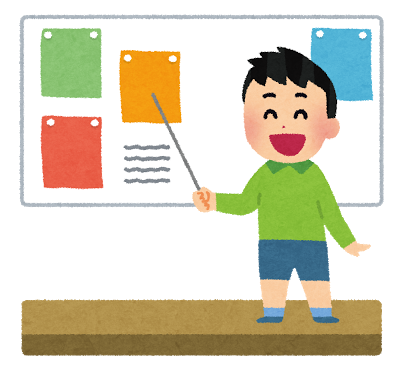
発表資料の作成前に聴衆を想像しよう!
ケモインフォマティクス・マテリアルズインフォマティクス・プロセスインフォマティクスの研究に限らず、研究成果が出たらその成果を論文や学会などで発表します。学会では、主にパワーポイントで発表資料を作成し、それを使って研究内容のプレゼンテーション...
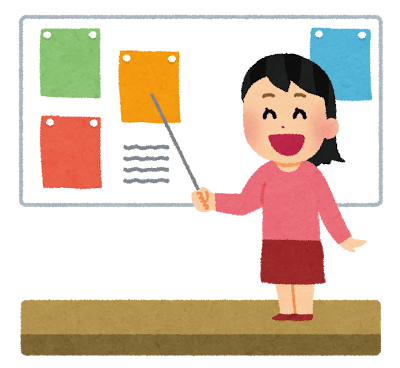
内容・結果を再現できる情報を発表スライドに入れよう!
口頭発表やポスター発表といった学会で発表する際のお話です。口頭発表の流れはこちらに書いた通りです。ポスター発表でも同じような項目をポスターに記載することになります。発表スライドやポスターを作成する際に、どこまで細かい情報をスライドやポスター...
発表資料を一通り作った後に、自分で見直しをして、より良い発表資料にする作り込みの作業があります。その際に意識することは、この発表を聞いた方々がどんな発表か、どんな質問をするかということです。その質問が明確に分かれば、その質問に答える形で発表資料を適切に更新できます。学会の趣旨、参加者の傾向といった内容をしっかり確認して、それを踏まえて質問を考えます。その想定質問に基づいて発表資料を作り直します。
そもそも、発表すること自体は目的ではなく、発表を聴いたが理解してくれることが目的です。そのため、発表者目線で考えることが大事です。ですので、逆に自分が発表を聴く側の時に、色々と質問を考えておくことが非常に重要です。自分の発表において、これまで自分が聴いてきた発表・内容に基づいて想像力を働かせて、どんな質問が来るかをしっかりと考えて発表資料を作り直します。ここでも想像力が大事です。
学会に参加した時には色々質問を考えることが、もちろん発表を集中して聞くことにもつながりますし、その後、自分の発表スライドの改善につながります。ぜひ、学会において発表だけでなく聴くことも十分に活用して、そして想像力を豊かにして、次の発表に臨んでもらえたらと思います。
ポスター発表も、同じ感じでポスターを作成するとよいですね。
以上です。
質問やコメントなどありましたら、X, facebook, メールなどでご連絡いただけるとうれしいです。

