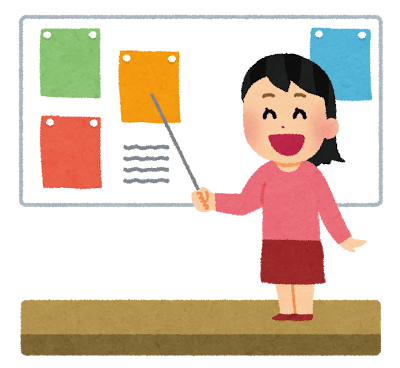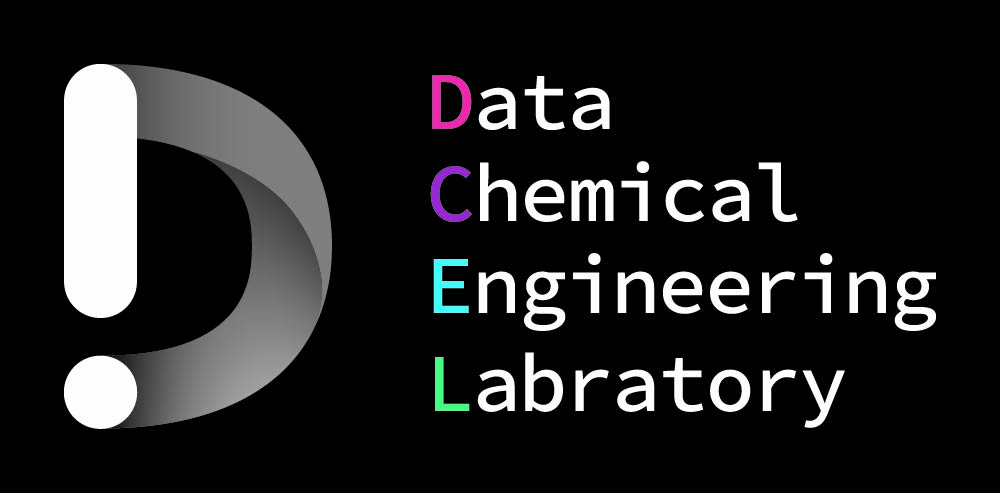論文を執筆する際や学会発表をする際に、提案手法などの伝えない内容をより分かりやすく説明するために、概略図・ポンチ絵を描くことがあります。概略図・ポンチ絵の目的は内容を分かりやすく説明することであり、芸術的な絵を描く必要は全くありません。伝わりやすく、わかりやすい絵にすることが大切です。
そのような概略図・ポンチ絵を作成する上で注意することについて、以下にまとめました。
- 図の中の文字の大きさを本文中の文字の大きさと同じにする:文字の大きさが小さすぎると読みづらくなります。逆に大きすぎると見る人に違和感が生じます。
- 色と言葉を揃える:例えば、説明変数xは赤、目的変数yは青で揃えるなどです。
- 図形の意味を揃える:同じ図形は同じ意味を表すようにします。例えば、同じ形状の矢印は「左から右への物の流れ」を表すのか「手順的な流れ」を表すのかを統一します。
- 見る人が「?」となることを避ける:変な隙間があったり、図形が揃っていなかったりすると、見る人は「何か意味がある?」と余計な思考が入ってしまいます。
- なるべくシンプルに表現できないかを(再)検討する:シンプルな図ほど分かりやすいです。似たようなものが繰り返し重複していないか確認し、できるだけシンプルな図で表現できるように見直しし、工夫します。
概略図・ポンチ絵が上手くなるためには、以上の注意点に加えて、論文や学会発表などで他人の概略図・ポンチ絵を見て、わかりやすい概略図・ポンチ絵について考えることも重要です。
以上です。
質問やコメントなどありましたら、X, facebook, メールなどでご連絡いただけるとうれしいです。